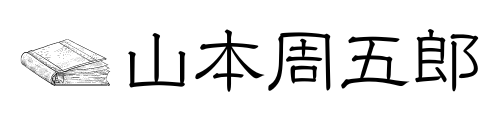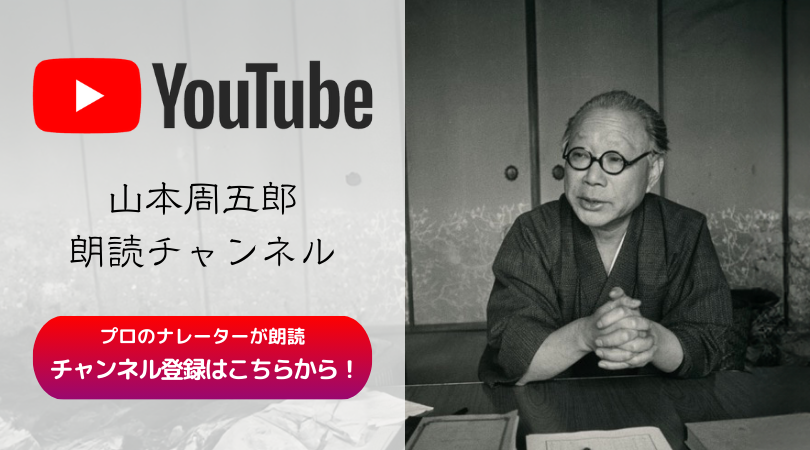『日本婦道記 郷土』

あらすじ
慶応四年(明治元年)、戊辰戦争の戦火が広がる中、戸部丈右衛門が庄屋を務める桑首村もその影響を受けていました。奥羽越列藩同盟を結成した会津藩と、明治新政府軍(征討軍)との戦いが激しさを増し、村では戦に備えて男たちが防衛の準備を進め、老幼婦女を避難させることが決定されます。
丈右衛門は、妻の竜や子供たち(長男金之助、次男千吉、長女美緒)を避難させるつもりでいました。しかし、そこへ戦火を避けて隣村の半道寺に滞在していた老母・清江が突然帰ってきます。丈右衛門が避難を勧めるも、清江は「ご先祖様の仏壇を守る」と言って動じません。
清江の強い意志と落ち着いた態度は、家族だけでなく村人たちの心を揺さぶります。特に、まだ幼い千吉でさえ「自分も武士の子だから戦の邪魔にはならない」と言い、長男の金之助や長女の美緒も「自分たちも残る」と言い出します。竜もまた、戦火を避けることに疑問を持ち始め、「家を守る」という強い覚悟を固めていきます。
この決意はやがて村中に広がり、避難を予定していた家族も次々と「村を守る」と言い出します。結果として、ほとんどの村人が踏みとどまり、村を守るために結束しました。その団結を目の当たりにした征討軍は、桑首村への攻撃を諦め、撤退していきます。
数日後、久保田城へ政府軍の援軍が到着し、戦局は変わりました。桑首村も戦火を免れ、村人たちは歓喜します。しかし、清江はあくまで平然とし、特別な祝いもしません。丈右衛門は、そんな母の姿を見て、「これこそが不動の心というものだ」と深く感じ入るのでした。
――祖先から受け継がれた土地と誇りを守るために。
武士の家族として、真に大切なものとは何かを問う感動の物語。