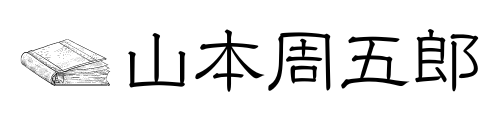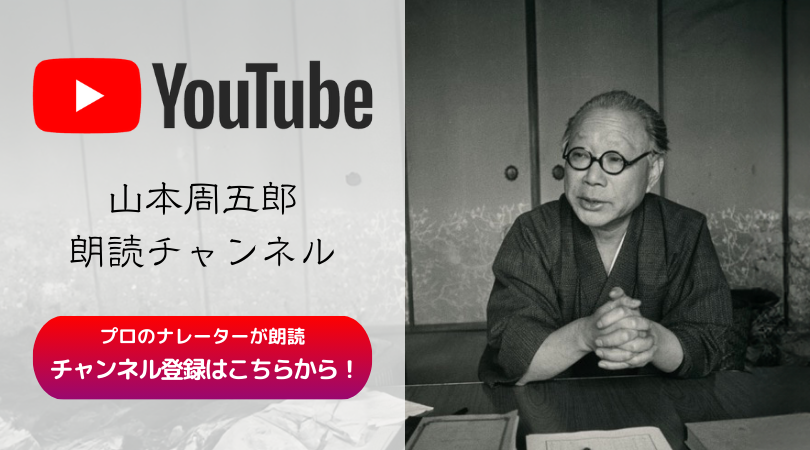『壺』

あらすじ
寛永12年(1635年)、紀伊国新宮の宿「万字屋」にて
ある日、木村外記(その正体は剣豪・荒木又右衛門)と名乗る中年の武士が、新宮の宿「万字屋」に滞在する。粗末な身なりながら、鋭い眼光と精悍な体つきをした彼は、物静かでありながらただ者ではない雰囲気を漂わせていた。しかし、彼の真意は誰にもわからず、ただ熊野詣での旅人を装っていた。
宿の裏で見た奇妙な剣術修行
外記が滞在中、宿の裏庭で妙な光景を目にする。ひとりの若者が、雨垂れの雫を抜刀で正確に斬り落としているのだ。彼の名は七郎次(瘤七)。新宮から熊野川を遡った三船村の農家の三男であり、幼い頃から人並み外れた怪力を持っていた。
七郎次はある日、旅の武士と喧嘩になり、あっさりと叩きのめされる。その悔しさから「自分が農民だから負けたのだ」「武士だったら負けるはずがない」と思い込み、農作業を捨てて剣の道を独学で歩み始める。松の枝を吊るして木刀で打ち続けたり、武術道場の下男となって技を盗み見たりしながら、少しずつ剣術を身につけた。やがて「万字屋」の下働きとなり、訪れる武士に試合を挑んでは勝ち続け、「瘤七(こぶしち)」の異名を取るようになる。
しかし、そんな彼を心から案じていたのが許婚のおぬいであった。彼女は七郎次に「元の農民に戻ってほしい」と願い、何度も説得を試みるが、七郎次はまるで耳を貸さない。
宿の新たな客と決闘の予感
ある日、「万字屋」に三人の武士が宿泊する。彼らは、かつて七郎次と戦って敗れた武士の仲間であり、七郎次に復讐を果たすためにやってきたのだった。七郎次は決闘を申し込まれ、それを受ける。
おぬいは彼が命を落とすのではないかと危惧し、助けを求めて外記のもとへ向かう。実は彼女は、以前、伊賀上野に奉公していた際、鍵屋の辻で名高い荒木又右衛門の姿を遠くから見たことがあった。そして、宿の客である木村外記こそが又右衛門本人であることを見抜き、「どうか七郎次を助けてほしい」と涙ながらに懇願する。
又右衛門、七郎次を救う
おぬいの必死の願いに動かされた外記(又右衛門)は、七郎次と三人の武士の立ち合いを見届けに行く。そして、戦いの最中に割って入り、「この勝負はすでに決した」として試合を中断させる。又右衛門の風格と説得力により、武士たちは勝負を放棄し、七郎次の命は救われる。
七郎次、又右衛門に弟子入りを願う
決闘を免れた七郎次は、又右衛門に弟子入りを志願する。「本物の武士になるため、どうか剣術を教えてほしい」と懇願する七郎次に対し、又右衛門は「剣の道を知りたければ、庭の杉の木の影を掘り、そこに埋められた壺を探し出せ」と言い渡す。
七郎次は、言われたとおりに杉の木の影を掘り始める。しかし、どこまで掘っても壺は見つからない。それでも彼は必死に土を掘り続け、雑草を抜き、石を取り除く。気がつけば、そこには見事に耕された畑が広がっていた。
壺の正体――本当に必要なものとは?
ある日、又右衛門は七郎次に「壺は見つかったのだ」と告げる。七郎次は驚くが、又右衛門は続ける。「お前はツボを探すために掘っていたはずなのに、気がつけば畑を耕していた。つまり、お前の手は自然と百姓の生き方をしていたのだ」と。そして、「武士とは、剣を振るう者ではなく、己を捨て、主君や国のために命を捧げる者だ。お前は本当にそれができるのか?」と問いかける。
七郎次はその言葉を聞き、初めて自分が本当に求めていたものが何だったのかを悟る。武士になることではなく、自分の生まれた場所で、精一杯生きることこそが本当の道であったのだ。
七郎次の決意と旅立ち
七郎次は己の過ちを悟り、又右衛門に深々と頭を下げ、「私は故郷に帰ります」と誓う。又右衛門は彼の決意を認め、形見として「鍬」を授ける。
そして翌朝、七郎次とおぬいは、静かに紀伊の国へと帰っていった。七郎次はもう、剣ではなく鍬を手に、百姓として生きる覚悟を決めていた。
結末――「壺」とは何だったのか?
又右衛門が示した「壺」とは、決して土の中に埋まっていたものではなく、「人が本当に進むべき道」を見極めることだった。剣術を極めることではなく、己の生き方を正すことこそが、本当の道だったのだ。