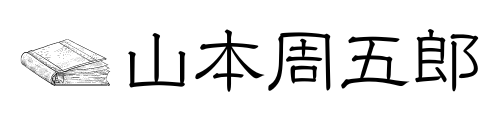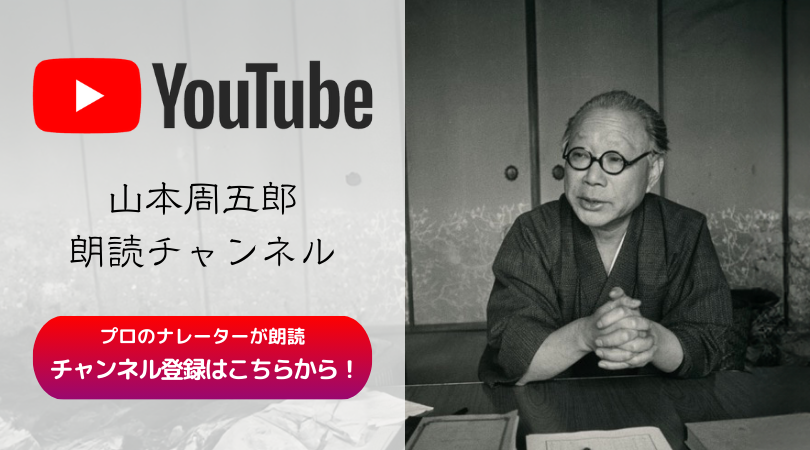『おかよ』

あらすじ
江戸の茶店で働くおかよは、幼い頃に親を亡くした孤児。ある日、同じく孤児であり、気の弱い足軽・印東弥次郎と出会う。仲間から孤立しがちな弥次郎を気遣い、少しずつ心を通わせるおかよ。彼の誠実さを知るにつれ、彼女は次第に深い愛情を抱くようになる。
やがて、島原の乱が勃発。弥次郎の主君である細川越中守忠利も出陣を命じられ、弥次郎にも戦場へ赴く運命が訪れる。しかし、戦が恐ろしい弥次郎は、できることなら行きたくないと怯えていた。そんな彼をおかよは懸命に励まし、戦場で身を守るための「鎌倉八幡宮の御守り」と称して、小さな包みを手渡す。それは実は、おかよが自らの肌身離さず持っていた守り札であった。
戦場では、敵の猛攻により味方は苦戦を強いられる。そんな中、勇猛な武士でさえ恐れる敢死隊(命を捨てて突撃する部隊)が編成されるが、弥次郎は足軽でありながら、植村七兵衛率いる三番隊に自ら志願する。戦の最中、彼は壮絶な銃撃の中を単身で駆け抜け、ついに敵の櫓(やぐら)にたどり着く。そして己の身を盾にして敵の銃撃を封じ、味方の勝利に大きく貢献するのだった。
戦いを生き延びた弥次郎は、江戸に戻り二百石の武士へと取り立てられる。しかし、意気揚々とおかよのもとへ向かう彼を待っていたのは、彼女の行方知れずという悲報だった。実は、おかよは最初から自分が武士の妻になれぬことを悟っており、弥次郎の将来のために姿を消していたのである。
後日、江戸郊外の茶店で語られる噂話。ある女が、おかよの話をしながら、「女は愛する人のために、一度だけでも役に立てれば、それで満足なのです」と呟く。その視線の先には、誰かを待っているような、遠くを見つめるまなざしがあった——。