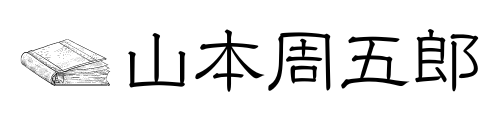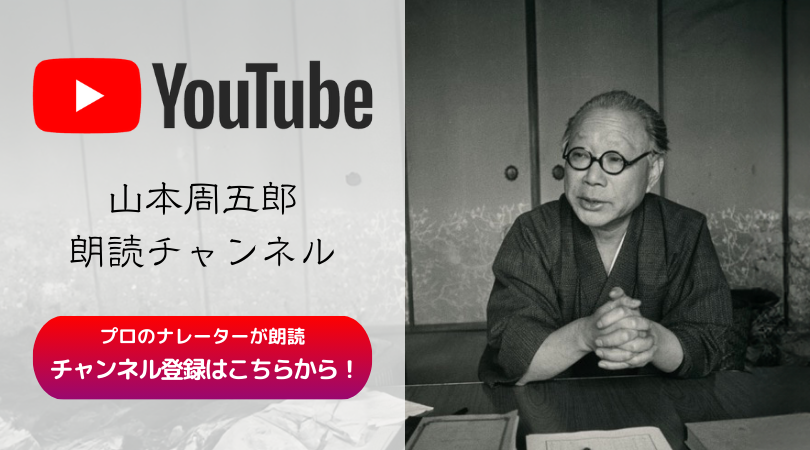『矢押の樋』

あらすじ
江戸時代、東北のある藩では、飢饉と凶作が続き、領民たちが困窮していた。藩は江戸幕府に借款を願い出るが、却下される。幕府との交渉に当たったのは、明敏で寡黙な藩士 矢押監物であった。彼は必死の嘆願を続けるが、ついに望みが絶たれ、責任を取って自害する。
藩内では、米の買い付けができず、領民の不満が爆発寸前に達していた。国家老 塩田外記や勘定奉行 外村重太夫らは対応に苦慮するが、有効な策を見出せない。そんな中、監物の弟であり、家老職の家柄に生まれながらも「乱暴者」と評される 矢押梶之助は、一つの大胆な決断を下す。
それは、城の内堀の水を切り、干ばつに苦しむ田畑に引くことだった。しかし、内堀の水は城の防衛に関わる重要な資源であり、その水を外へ流すことは禁じられていた。藩の掟に背く行為であるため、上層部は猛反対する。しかし梶之助は密かに 吉井幸兵衛ら農民と協力し、内堀の石垣に樋を通す計画を進める。
一方で、梶之助が出入りしていた吉井家の娘 加世は、彼に淡い想いを寄せていた。しかし、梶之助は己の使命を果たすため、加世との未来を諦める。
やがて、梶之助の計画は国家老・塩田外記に露見し、阻止されそうになる。しかし彼はなおも実行を強行し、仲間とともに城の石垣を崩し始める。そこへ駆けつけた外記に向かい、「江戸城ですら石垣が崩れたことがある」と言い放ち、これは自然崩壊だと主張。ついに内堀の水は解き放たれ、干ばつに苦しむ田畑へと流れていった。
しかし、梶之助はその場で石垣の崩落に巻き込まれ、命を落とす。その後、内堀には正式に水門が設けられ、それは「矢押の樋」と呼ばれた。
物語のラストでは、樋のほとりに静かにたたずむ加世の姿が描かれる。彼女の胸には、志を貫いた男への想いが秘められていた——。