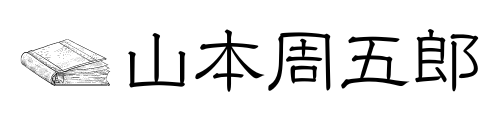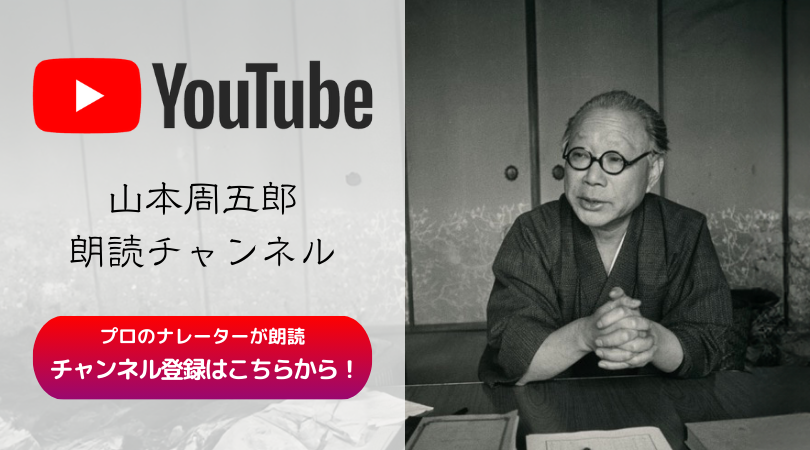『鏡』

あらすじ
江戸時代、幕府の威信をかけた重要な決断が求められる事件が発生する。江戸城二の丸で、水戸藩士と幕臣の間で諍いが起こり、水戸家の家臣が本丸の幕臣を斬るという事件が発生した。幕府はこの事件を重く見て、幕臣を斬った水戸家の家臣の引き渡しを求めたが、水戸藩主・水戸頼房はこれを拒絶する。
幕府の老中たちは困惑し、三度にわたり使者を送るが、いずれも水戸藩の強硬な態度に阻まれる。幕府の威信を守るためには、水戸藩を従わせねばならないが、無理に押し通せば、幕府と水戸藩の間に決定的な対立が生じかねない。老中の中心人物である安部豊後守忠秋は、この難局にどう対処すべきか苦悩する。
そんな中、忠秋の妻・朝子が何気なく語った「鏡」の話が、忠秋に大きなヒントを与える。彼女は、召使いの娘・鷺(さぎり)が化粧を覚え始めたものの、まだ上手にできず周囲に笑われていたことを話す。しかし、朝子は直接注意するのではなく、一枚の鏡を渡したところ、鷺は自らの姿を見て徐々に改善していったという。この話を聞いた忠秋は、人に何かを悟らせるには、直接押し付けるのではなく、本人が自ら気づくように仕向けることが重要だと考える。
翌日、忠秋は平服で水戸屋敷を訪れ、雑談の流れで、徳川秀忠の遺言書について話を持ち出す。そして、水戸頼房自身にその遺言書を読み上げさせ、そこに明記されている「喧嘩両成敗」の原則を自覚させる。頼房は、自分の判断が先代将軍の意志に反していることを悟り、ついに幕府の要求を受け入れる決断を下す。
結果的に、水戸藩の家臣は切腹を命じられ、幕府と水戸藩の衝突は回避された。忠秋は、妻の「鏡」の話を心に刻み、相手に直接命じるのではなく、自ら気づかせることの重要性を再認識するのだった。