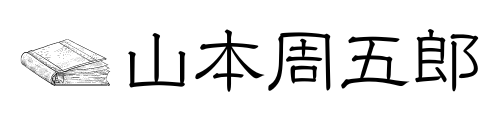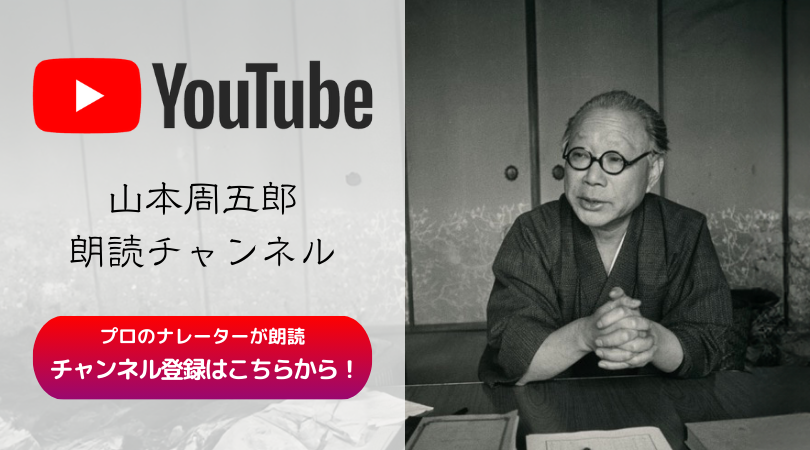『笠折半九郎』

あらすじ
紀伊家の中小姓・笠折半九郎と畔田小次郎は親友だったが、半九郎の婚約者・瑞枝の琴の話がきっかけで口論となり、翌朝の決闘を約束する。しかしその夜、和歌山城で大火事が発生し、小次郎が半九郎の屋敷に立ち寄り、火事装束を持参して迎えに来る。二人は急ぎ城へ戻り、それぞれの持ち場で奮闘。半九郎は火の中で宝物を運び出し、角櫓を死守した。
火事後、多くの者が恩賞を受けるが、半九郎には何の沙汰もなかった。周囲の噂が広まり、「半九郎が火事場の恩賞は火消人足と同じと言った」と誤解が生じる。仲間たちが詰問する中、半九郎は謝罪を拒否し、小次郎と再び決闘をすることに。
翌朝、決闘の場に現れたのは小次郎ではなく、主君・徳川頼宣だった。頼宣は半九郎を殴り、「恩賞を与えなかったのは、家臣の命を守るためだ」と諭す。そして、二人に50日の閉門処分を言い渡し、「小次郎は半九郎の家で共に謹慎せよ」と命じる。こうして二人は和解し、半九郎は瑞枝の琴を聴いて心を広くすることを誓うのだった。
本作は、武士の誇り、友情、名君の裁断を描いた作品であり、人間の成長と真の忠義を考えさせる物語である。
書籍
朗読
本文
喧嘩は理窟ではない、多くはその時のはずみである、理窟のあるものならどうにか納りもつくが、無条理にはじまるものは手がつけられない、笠折半九郎と畔田小次郎との喧嘩がその例であった。
二人は紀伊家の同じ中小姓で、半九郎は西丸角櫓の番之頭を兼任し、食禄は三百石、小次郎は二百五十石を取っていた。……年齢は半九郎の方が二歳年長の二十七であるが、気質からいうと小次郎の方が兄格で、烈しい性格の半九郎とはちょうど火と水といった対照であった。
半九郎も小次郎も早くから主君頼宣の側近に仕えて二人とも別々の意味で深く愛されていた。半九郎はその生一本な直情径行を、小次郎は沈着な理性に強い性格を、そして二人はまた互いに無二の友として相許していた。
そのときの喧嘩がどういう順序で始ったかよく分らない。城中の休息所で座談をしているうち、話がふと半九郎の縁談に及んだ。……彼はそのとき同藩大番組で八百石を取る天方仁右衛門の娘瑞枝と婚約が定まっていた。瑞枝は才女という評判が高く、特に十三絃に堪能でしばしば御前で弾奏したことがある、話は自然とその琴曲のことになった。小次郎は半九郎が武骨者で、芸事などには振向いても見ないのを知っていたし、瑞枝の琴の話が出ると、明かに不快そうな顔つきになるのを認めたから、ちょっと意地悪な気持になって、
――笠折もこれから瑞枝どのの琴を聞いて、心を練る修業をするんだな、音楽というものは人の心を深く曠くするものだ。
というような意味のことを云った。
それがいけなかった、ごく親しい気持から出た言葉ではあるが、時のはずみで半九郎は真正面から喰い下った、おんなわらべの芸事などで心を練り直さなければならぬほど武道未熟だというのか、そう開き直ったのがきっかけで暫く押し問答をしていたが、ついに半九郎は面色を変えて叫びだした。
――このままでは己の面目が立たぬ、それほどの未熟者かどうか試してみよう、明朝卯の刻に城外鼠ヶ島で待っているから来い。来なかったら家へ押掛けるぞと云って、半九郎は下城してしまった。
屋敷へ帰った彼は、仲裁役でも来ると面倒だと思って、後事の始末を書面にして遺し、そのまま城下から南へ三十町あまり離れた、砂村の農夫弥五兵衛の家に立退いた。……弥五兵衛はもと笠折家の下僕であったが、数年まえに暇を取り、今では妻子五人で農を営んでいた。
半九郎は自分の怒り方が度を越しているのを知っていた。時間の経つに順ってその感じがはっきりして来た、どう考えても果合いをするほどの問題ではない。
――いけなかった、やり過ごした。
そう思った。けれどまた直ぐそのあとから、新しい忿がこみあげて来た。小次郎の言葉には親しい者だけに共通する意地悪さがあった、己が云うなら許されるだろうという、狎れた意地悪さが隠されていた。
――どれほど親しい間柄でも、云って宜いことと悪いことがある、武士の心得を座談にして弄ぶ法はない。
彼は武骨者で茶花風流には暗かった。武士には要のないものだと云ってはいたが、そういうものに興味を持てないことは、自分でも私に弱点だと思っていた、そしてそう自覚しているだけ余計に、遊芸に類するものを軽侮していたのである。……つまり小次郎はそれを承知して、彼のいちばん痛いところを突いたのである。
「明日の朝五時に起して呉れ」
弥五兵衛にそう云って、半九郎は宵のうちに寝た。
なかなか眠れなかった。
ともすると苦い後悔の感じが湧いて来るので、なるべく忿怒を煽るようなことだけを考えた、空想は鼠ヶ島の決闘の場面まで発展した、無二の友達同志が刃を噛合せている様や、血まみれになって倒れている小次郎の姿などは、空想のなかで一種の快感をさえ呼起した。
そうしているうちに、いつか考え疲れて眠ってしまったらしい。雨戸を叩くけたたましい物音に、半九郎が恟として眼を覚ますと、
「笠折はいないか」
と呼びたてる声が聞えた。
「ちょっと起きて呉れ、笠折半九郎は来ていないか」
――小次郎だ。
半九郎はがばとはね起きた。
「よし、己が自分で出る」
起きて来た弥五兵衛を押止め、手早く身支度をした半九郎は、大剣をひっ掴んで、手荒く縁側の方の雨戸を明けた。
「半九郎は此処にいるぞ」
「おっ、笠折いたか」
叫びながら走って来る小次郎を見て、
「約束は卯の刻、場所は鼠ヶ島と云った筈だ、血迷ったか小次郎」
「それどころではない、あれを見ろ」
小次郎は叫びながら手を挙げてうしろを指した。
まだ空は全く暗かった。満天の星は朝の霜のひどさを思わせるように、きらきらと研ぎ澄ました光を放っている、……その星空の下に、ぼっと赤く、大きな篝火のような光暈の拡がっているのが見えた。
「火事だ、しかもお城の大手に近い」
半九郎は慄然と身を震わした。
「西丸御門外の武家屋敷から出たが、この風で火は今お城へ真向にかかっている、笠折」
小次郎は持っている物を差出しながら、
「いま貴公の家へ立寄って、多分此処だと思ったから火事装束を持って来た、馬も曳いて来てある、果合いは又のことだ、貴公は櫓番の頭だぞ」
「小次郎、かたじけない」
半九郎はひと言、呻くように云うと、友の差出した包を取ってひらいた、夢中だった、踏込み袴、定紋付きの胸当、羽折、兜頭巾、それに腰差し提燈まで揃っている、彼はそれを身に着けながら、
――やはり友達だった。
となんども胸いっぱいに叫んだ。
弥五兵衛が提燈に火を入れるのを、ひったくるようにして外へ出た、表には馬が二頭繋いであった、二人は轡を並べて駆けだした。……往還へ出るとはじめて烈風を感じた。半九郎は空を焦がすような遠い火を睨んで、容赦もなく馬に鞭を呉れながら疾駆した。心は湯のような感動でいっぱいだった、宵のうちの悔恨はもう無かった。男同志の友情の有難さが、ただそれだけが、彼の全身の血をかきたてた。
大番町へ入ったところで二人は馬首を分った、半九郎は西丸口へ、小次郎は大手へ。
「小次郎!」
別れるとき半九郎が叫んだ、
「忘れぬぞ!」
小次郎は振返った。にっと僅に笑った白い顔が、半九郎の眼に鮮やかな印象を焼きつけた。彼はそのまま馬を煽って行った。
明暦元年十一月十九日早朝四時、和歌山城西丸御門の外にある都築瀬兵衛の屋敷から出た火は、おりからの烈風にみるみる燃え拡がり、一方は武家屋敷から町家の方へ延び、一方は西丸の門から城へと移った。……そのとき頼宣は伊勢へ鷹野に出たあとで、久野和泉守が留守を預かっていた。留守城のことで人数も足りなかったし、旱天続きで乾いてもいたし、おまけに珍しいほどの烈風で、城へ移った火は防ぎようもなく延焼した。
半九郎が西丸の角櫓へ馳けつけたとき、十七人の番士は一人も欠けず揃って、櫓前へ水を運んでいるところだった。……半九郎は砂丸を焼く火が、御宝庫の上にのしかかっているのを見た。
「お蔵が危い、お蔵番はいないのか」
なんども叫んだが人の姿はなかった。……彼は躊躇なく番士五人を連れて馳けつけると、鍵をうち壊して扉を明け、文字通り火を浴びながら、秘蔵の宝物を取出して角櫓へ運んだ。
「此処も危のうございます。お山へ移した方が安全でございましょう」
「此処が危いと?」
番士の言葉を半九郎は烈しく極めつけた。
「馬鹿なことを云え、このお櫓を焼いてなるか、十七人全部死んでもこのお櫓は守り通すのだ、我々の死に場所は此処だ、一歩も退くな」
すでに西丸が焼けていた。櫓の上に登った半九郎は、二の丸の大屋根を抜いて噴きあげる の柱を見た。右も左も火
の柱を見た。右も左も火 だった。耳を聾するような
だった。耳を聾するような の叫びと、建物の焼け落ちる轟きと、物のはぜ飛ぶ劈くような響が、怒濤のように揉み返していた。……煙は火を映しながら、まるで生き物のように立昇り、恐ろしい渦を巻いて崩れたかと見ると、八方に翼を拡げて地を掃き、再び空へと狂気の如く舞いあがった。
の叫びと、建物の焼け落ちる轟きと、物のはぜ飛ぶ劈くような響が、怒濤のように揉み返していた。……煙は火を映しながら、まるで生き物のように立昇り、恐ろしい渦を巻いて崩れたかと見ると、八方に翼を拡げて地を掃き、再び空へと狂気の如く舞いあがった。
砂丸を焼いた火と、西丸を焼く火とが、両方から多門塀を伝って近づいて来た。
「みんな此処で死ね、一人も退くな」
半九郎は繰返し叫んだ。
「卑怯な真似をする奴は斬るぞ!」
息もつけぬような煙が巻いて来た。煽りつける火気は肌を焦がすように思えた。……襲いかかる火の粉を必死と払いながら、半九郎は火の海のなかに、力強く屹然と立っている天守閣の壮厳な姿を見た。それは大磐石の姿だった。
――大丈夫だ、この櫓は助かる。
彼は神を信ずるようにそう確信した。
事実その櫓は焼けなかった。十七人の死を賭した働きが、ついに猛火を防ぎ止めたのである。半九郎をはじめ多少ともみんな火傷をした。手を折った者もあった。誰の衣服も焦げ跡のないものはなかった。鬢髪の焼け縮れていない者はなかった。しかしそんなことはなんでもなかった。櫓は助かったのだ。彼はその本分を尽したのである。
――小次郎、己はやったぞ。
火勢の落ちた和歌山城の上に、ようやく朝の光が漲りわたるのを見ながら、半九郎はつきあげるような思いで独り叫んだ。
――やったぞ、己はやったぞ小次郎。
急を聞いて頼宣が帰ったのは、それから二日後のことであった。
天守閣と櫓の一部が残っただけで、城はほとんど焼けていた。城外では武家屋敷六十軒、町屋敷百九十五軒、町数合せて九十余という大火であった。……火を失した都築瀬兵衛は、親族から切腹を迫られたが、結局は遠島ということに定った。
帰城した翌々日、頼宣は湊御殿に留守役の者を呼んで、防火の労を犒い、またそれぞれ恩賞の沙汰をした。焼け落ちた西丸、二の丸、砂丸の番士たちにも恩命があった。半九郎も伺候していたが、彼にはなんの言葉もなかった。……そして恩賞にあずかった人々が次ぎ次ぎと去って、最後に彼だけが残ったとき、ようやく頼宣が近うと呼びかけた。そして火事場のことには一言も触れず、
「半九郎、その方出火の当日喧嘩をしたそうではないか」
と意外なことを云った。
「仔細はどうでもよい、小次郎に果合いを挑んだというのは事実か」
「恐入ります、些かとりのぼせまして」
「それでどうした、始末を申してみい」
「恐れながら……」
半九郎は腋の下に汗をかいて平伏した、思いも懸けぬことを突込まれて、ちょっと言句に詰ったのである。
「申してみい、果合いの始末をどうした」
頼宣はたたみかけて促した。
半九郎は平伏したまま始終の事を述べた、頼宣は黙って聴いていた。半九郎の言葉が終ってからも、暫くのあいだ黙っていた。……自分の口から仔細を述べるうちに、半九郎は悔恨と自責の念が新しく甦って来るのを感じ、黙っている頼宣の無言の叱責が、千貫の重さで頭上へのしかかるように思えた。
「友達というものは有難いものだな」
頼宣がやがて感慨の籠った声で云った。
「小次郎は思慮の深いやつだ、しかし小次郎だけが秀でているとは云わぬ、友達の情の美しさだ、おろそかに思ってはならぬぞ半九郎」
半九郎は噎びあげていた。
「その方は一徹で強情が瑾だ、そこが良いところでもあるし、また禍を招く素でもある、もう少し分別を弁えぬといかんぞ」
そう云って頼宣は立った。
火事場のことについては一言の沙汰もなかった。半九郎はむろんそんなことは意に留めなかった。自分はするだけの事をしたのである、しかもその火事は偶然にも自分と小次郎との友情の証しとなって呉れた。それだけでも充分だと思った。
けれど世間の人々はそう簡単に済まさなかった。当時の昂奮が冷めて来ると、人々の眼は半九郎のうえに集りだした。
――笠折に恩賞のお沙汰がないのはどうしたのだ、彼は十七人の番士と身命を賭して、角櫓を火から救ったではないか。
――そうだ、笠折はお蔵から御秘蔵の宝物をも運び出している。
――持場を焼いた者たちでさえ恩典があったのに、もっとも手柄を立てた笠折に、なんのお沙汰もないというのは不審だ。
――なにか仔細があるのだろう。
そういう噂話が、おりに触れると半九郎の耳にも入るようになった。彼にとっては迷惑であり不愉快な話であった、自分では恩賞に漏れたことなど少しも考えてはいないし、するだけの事をしたのだという気持で落着いている、だからそんな噂を聞くと、自分までが卑しく、さもしい感じになってやりきれなかった。
ある日四五人集っているところで、またその話になったとき、半九郎は我慢ならぬという調子で云った。
「いったい貴公たちはなんの用があってそんなことをつべこべ云うのだ、拙者は恩賞を賜わるような働きはなにもしてはいないぞ、自分の責任を果したまでだ、誰でも当然なすべきことをなしただけだ、火消人足ではあるまいし、火事場の働きで恩典にあずかろうなどというさもしい考えは微塵もないぞ、つまらぬ話はいい加減にやめろ、馬鹿げている」
「おい、……笠折、それは少し言葉が過ぎはしないか」
一人が急に眼を光らせて乗出した。
「我々は誰のために云っているのでもない、むろんお上に対して御批判申すのでもない、ただ身命を賭して御宝物を救い、お櫓を守ったという事実を云うのだ、持場を焼いた者たちにさえ恩賞があったのに、それだけの働きをした者になんのお沙汰もないという事実を云っているんだ。……それに対して火消人足でないとは言葉が過ぎるぞ」
半九郎はむかむかと忿がこみあげて来た。しかし懸命にそれを抑えて黙っていた。……相手は書院番の麻苅久之助という、小意地の悪い女のように嫉妬深いので有名な男だった。口の下手な半九郎などの敵すべき相手ではない、それで哀しくも彼は沈黙を守った。
「火消人足とは変なことを云う」
相手は鬼の首でも取ったように、なおも執念く傍の者を捉えて続けた。
「自分はなにか理由があるとして、取澄しているならそれで宜いさ、しかし傷だらけになって、命を的に働いた十七人の組下が可哀そうではないか、火消人足ではないなどと、見当違いなことを云う暇があったら、少しは組下のことも考えて遣るべきだ」
「拙者はこういう話を聞いているんだが」
久之助のねちねちした態度をとりなすように、一人が側から口を んだ。
んだ。
「なあ笠折、あの日貴公はお上から、畔田と喧嘩をしたことでお叱りを受けただろう、是は単なる噂にとどまるかも知れんが、畔田がお上にその事を申上げたので、それでお上がお怒りになったということを聞いたぞ」
「それは有りそうなことだ」
別の一人が頷いて云った。
「畔田としては城中満座のなかで果合いを挑まれたのだからな、その返報としてもそのくらいのことは有るかも知れん」
「止めて呉れ、どうかみんな止めて呉れ」
半九郎は堪り兼ねて云った。あまりその声が悲痛だったので、みんな驚いて眼をあげた。半九郎は抑えつけたような声で、まるで自分自身に挑みかかるように云った。
「畔田がどんな人間か、拙者は誰よりも熟く知っている、そういう噂は人を毒するだけだ、どうかもう蔭口や噂は止めて呉れ、十七人の組下に対しては、拙者が直ぐに番頭としての責任を執る、だからもうこんな話は是だけで打切りにして呉れ、もう沢山だ、本当にもう沢山だ」
それだけ云うと、半九郎は立ってその席を去った。
櫓番の支配は寄合役である、半九郎は辞表を支配役に差出して下城すると、家人に酒を命じて強かに呑みはじめた。
……彼は自分の執った態度が、いつかのようにとりのぼせたものだということに気付いていた、小次郎に果合いを挑んだときとは原因がまるで違う、しかしその憤激のかたちには同じ苦しさがあった。心の隅には早くも、あのときと同じ悔いが孕んでいた、でも彼にはどうしようもなかった。
酔いが廻るにつれて、いろいろな人の顔や、言葉や、態度が、次ぎ次ぎと眼にうかんで来た。みんな誹謗と嘲笑の相であった。
――こんなことを考えてはいけない。
彼はなんども反省した。胸へこみあげて来る毒々しい妄念を否定するように、烈しく首を振っては酒を呷った。
――己には己の生き方しか出来ない、嗤う者は嗤え、己は自分の正味を投出している。是が笠折半九郎だ。
泥酔した彼は寝た。
翌日はひどく頭が重く、悪酔いをした胸苦しさがいつまでも消えなかった。それで彼は再び酒を命じた。……午近くになって、支配役から出仕を促す使者が来た。半九郎は家士を挨拶に出して、
――所労で臥せっているから、追って本復のうえ登城する。
と答えさせた。
使者は別に深い穿鑿もせず、大切にするようにと云って去った。……半九郎にはそれが空々しい言葉に思われた、そしてそう思ったときから、彼の考え方は新しい方向へ曲がりだした。
彼は改めて恩賞のことを思いだした。どうして自分だけになんの沙汰もなかったのか、もし小次郎との喧嘩が悪いなら、小次郎にも同じ咎めはある筈だ。しかし小次郎はみんなと同様に恩典にあずかっている。
――こいつは考える値打があるぞ。
彼は続いて、小次郎が自分より先に、喧嘩の始末を言上したという話を思いだした。
畔田は思慮の深いやつだ。
そう云った頼宣の言葉も耳に残っている。思慮が深いということは、彼のように馬鹿正直でないという意味にもなる、彼の生一本な気持では為し得ない多くのことを為し得るという意味にならないか? ……彼はなんの隠しもなく喧嘩の始末を申し述べた、しかし思慮の深い小次郎が果して同様の言上をしただろうか。
「そうだ、火事の朝もそれだ」
半九郎は思わず声をあげて呟いた。
「もしあの火事がなかったら、あいつ果して鼠ヶ島へ来たろうか、……否! 来はせぬ、あいつは己の剣を知っている、来るとしても仲裁人か、そう見せて助太刀を連れて来たに違いない。火事はあいつに取って一石二鳥だった、果合いを免れたうえに、馬鹿正直な己をまんまと泣かした、くそっ!」
半九郎は拳で力任せに膝を叩いた。
斯うなると、考えることはそんな自分を唆しかけるものだけになる、なんでも宜い底の底まで自分を追い詰めて、胸に溢れている妄念を一挙に爆発させてみたい、そういうすてばちな衝動が全く半九郎を捉えてしまった。……ちょうどそこへ、まるで油へ火を投げるような事が起ったのである。
「申上げます」
家士の五郎次が襖を明けた。
「呼ばぬうちは来るなと申してある、退れ」
「お客来でございます」
「会わん、誰にも会わんぞ、病臥して居ると云って追い返してしまえ」
「そうお断り申したのですが」
家士は困惑した様子で云った。
「病床でなりとも達てお眼にかかりたいと、みなさま押しての仰せでございます」
「みなさま? ……誰と誰だ」
「柳河三郎兵衛さま、殿村靱負さま、長谷部伝蔵さま、由井、大道の方々でございます」
西丸詰め、二の丸詰めの者たちで、ことに大道市次郎と由井十兵衛は番頭格であるが、孰れもそう親しく往来している訳ではない。
「会ってやる、通して置け」
半九郎は支度を直しに立った。
客間に待っていた五人は病床の見舞いを述べるでもなく、押して面会を求めた釈明をしようともせず、半九郎が座につくのを待兼ねたように、由井十兵衛が直ぐ要談をはじめた。それは半九郎にとって全く思懸けぬ問題であった。
「先日城中で、貴公は火事場の恩賞について麻苅たちと話をしたそうだな」
「拙者から持ち出した訳ではないが、その話ならした」
「貴公そのとき、火事場の働きで恩賞にあずかるのは、火消人足も同様だと云ったそうだが、相違ないかどうか聞きに来たのだ」
半九郎は平手打ちを喰ったような気がした、麻苅久之助に云った言葉が、今やまるで違う意味をもって、しかもかなり重大な内容を帯びて返って来たのだ。
「如何にも、そういう風なことは云った」
彼は出来るだけ静かに説明しようとした。
「そういう風なことは慥に申したが、しかしまた貴公が云った通りではない、言葉は似ているが意味は違う」
「どう違うか聞こう」
「拙者は自分のことを云ったのだ、各々も耳にしていると思うが、あのとき拙者だけは恩賞のお沙汰がなかった」
「それが貴公には不服なのか!」
いちばん若い長谷部伝蔵が叫んだ。
「……そうではない」
半九郎は自分を抑えて続けた。
「そうではないんだ、周りの者がそれを云うんだ、拙者は自分の為すべき事を為しただけで、恩賞の有無などは些かも考えてはいない、それなのに周りの者がいつまでもその評判をするんだ、あのときもそうだった。拙者にはうるさいし、迷惑なんだ、それで自分はそんな火消人足のようなさもしい考えは持たぬと云ったんだ」
「では改めて訊くが、火事場の働きで恩賞にあずかった者は、火消人足も、同様だと云うんだな」
「話すことを、拙者の話すことをもっと熟く聞いて呉れ、そうではないんだ」
「そうでなければどうだと云うんだ!」
柳河三郎兵衛が大声に喚いた。
「持って廻った言訳は止めろ、我々は防火の手柄をお褒めにあずかった、御恩典を受けている。貴公の言葉は我々に取って聞き せぬ重大な意味を持っているぞ」
せぬ重大な意味を持っているぞ」
「恩賞を受けぬ貴公は宜いだろう、しかしその言葉は我々一同を火消人足と申したも同じことになるぞ笠折、確と返答を聞こう!」
半九郎は出来る限り自分を抑えていた、しかしどう説明しても、言葉の持っている本当の意味は分って貰えないと思った。
「ええ! 面倒だ」
半九郎は頭を振って云った。
「これだけ云っても分らないなら、どうでも好きなように解釈しろ、なんとでも勝手に僻め、拙者はそんな馬鹿な相手はもう御免だ」
「それは正気で云う挨拶か!」
「笠折、庭へ出ろ!」
伝蔵が大剣を掴みながら叫んだ。そのとき、廊下を畔田小次郎が走って来た、彼は五人が押掛けたと聞いて追って来たのである。
「待て、みんな待って呉れ」
小次郎は座敷へ入ると、今しも総立ちになった客と主人との間へ、そう叫びながら割って入った。そして先ず半九郎を押えつけ、
「笠折へは拙者が話をする、みんなとにかく待って呉れ、手間は取らさぬ、さあ……向こうへ行こう笠折、宜いから来るんだ」
そう云いながら、引摺るように半九郎を居間の方へ連れて行った。
「落着け、落着いて聞くんだ笠折」
半九郎を引据えながら、小次郎は声を励まして云った。
「貴公の言葉は穏当ではない、いや分ってる、貴公がそう云った時の意味は別だった、しかしそれが彼等に伝われば、斯ういう問題が起らずにはいないものを持っている、言葉が悪かったんだ、拙者の云う気持は分るだろう」
「簡単に云え、己にどうしろと云うんだ」
「云い過ぎたということを一言で宜い、行って彼等に詫びて呉れ、ただ形だけでも宜い、あとは拙者が旨く片を付ける」
「あのときのようにか」
半九郎は白く笑いながら云った。
「お上へ喧嘩の始末で言上したように、あの時のように旨く片を付けるか、小次郎」
「なにを云う。……貴公酔っているな笠折」
「真直に己の眼を見ろ!」
紙のように蒼白めた顔を、ぐっと突き出しながら半九郎は叫んだ。
「宜いか小次郎、己はこれまで世間の評判や噂話などは軽蔑して来た、そんなものは人を毒するだけで、三文の値打もないと思って来た、ところがそうじゃなかった、三文の値打もないどころか、そいつは人の運命を左右することも出来るんだ、大切なのは人間じゃない、言葉だ、噂だ、蔭口やこそこそ評判だ、腹黒い奴がひと捻り捻るだけで、事実には関係なしに言葉が人間の運を決定するんだ。宜いか、……是だけのことを前提として、あの五人に詫びると云うなら、己は詫びる」
半九郎はもういちど白く笑って続けた。
「だが小次郎、そのまえに己は云うことがある、今度の紛争の原因は、己が恩賞のお沙汰に漏れたことにあるんだ、そしてその原因の前にもう一つ本当の原因がある、……そいつを先ず解決しなくてはならん」
「それはどういう意味だ」
「鼠ヶ島の果合いだ、あれが己から恩賞のお沙汰を奪った、十七人の組下までがそのために恩賞から漏れた」
「笠折、それは正気で云うことか」
小次郎の眼にも忿が表われた。
「拙者も世間の噂はうすうす聞いていた、拙者がお上に、喧嘩のことで貴公を讒訴したという、馬鹿げた話で取るにも足らぬと捨てて置いたが、貴公それを信ずるというのか」
「五人に詫びろと云うまえに、貴様はそれを考える必要があったんだ、取るにも足らぬこそこそ話が、人の運を決定するんだ、己は今こそ悪意を認める、己が五人に詫びるまえに貴様は鼠ヶ島の借を返さなくてはならんぞ」
「心得た、如何にも鼠ヶ島へ行こう」
小次郎はそう云いながら立った。
「今度は拙者から時刻を定める、明日の朝六時、必ず待っているぞ」
半九郎は荒々しく去って行く小次郎の姿を、嘲笑の眼で見送った。……それから更に彼が、客間で待っている五人に、こう云っている声を聞いた。
「笠折とは拙者が果合いをすることに定めました。各々は手をお引き下さい、拙者には前からの行懸りがあるのです、笠折のことは拙者にお任せ下さい」
決意のある声だった、それに対して五人の方でもなにか主張したが、結局は小次郎に任せると決ったらしい。……半九郎はそれを聞きながら、
「誰か居らぬか、酒が無いぞ」
と大声に叫びたてた。
この争いには自然でないものが多い。つまらぬ感情のささくれや、行違いや、思過しや、いろいろな要素が偶然にひとところへ落合い、それが誤った方向へ押流されている。……半九郎にしても小次郎にしてもそれが分らない訳ではなかった。しかし斯うしたやりきれない紛擾は、いちど行き着くところまで行かぬ限り、解決のしようがないのである。そして最も信頼する相手を最も卑しく考えるという、非常に矛盾したことが、この場合には極めて自然な成行きになってしまったのだ。
明くる朝、半九郎はまだ暗いうちに起きた。……霜のひどい朝だった、裸になって頭から何杯も水を浴び、新しい肌着に、継ぎ裃で支度をした。そして食事はせずに家を出た。
供を連れなかった。足の下に砕ける霜の音を聞きながら、ようやく明けはじめた早朝の町を、なにも考えずに砂村の方へ急いだ。
鼠ヶ島は紀ノ川の砂洲の発達したもので、実生の松が僅に林をなし、周囲は枯れた蘆荻が叢立っていた、……朽ちかかった踏板を渡って島へ登ると、乳色の川霧を震わせて、千鳥がけたたましく舞い立った。
――まだ来て居らんな。
ひとわたり見渡して、そう呟きながら、半九郎は小松原の方へ入ろうとした。すると、それを待受けていたように、松のあいだから進み出て来た者があった。
「……小次郎か」
半九郎は五六歩あとへ跳び退って、大剣の柄へ手をやった。
相手は構わず近寄って来た。そして、川霧を押分けてその姿をはっきりと示したとき、半九郎はいきなり眼に見えぬ力で突き飛ばされでもしたように、あっと叫びながらよろめいた。
近寄って来たのは頼宣であった。
「抜け、抜け半九郎」
頼宣は静かに呼びかけた。
半九郎は即座に大剣を鞘ごと腰から脱り、それを遠く投出しながら、砂上に平伏した。……頼宣は大股に歩み寄って、砂上に伏した半九郎の側へ片膝を突くと、左手でその衿を掴み、拳をあげて頭を殴りつけた。
「馬鹿者! 馬鹿者、馬鹿者!」
三つ、四つ、五つ、痺れるように痛い拳だった。しかしその痛さは、そのまま頼宣の愛情の表白であった、半九郎はその痛さを通して、大きな主君の愛情を直に感じ、これまで自分を毒していたあらゆる妄念が、そのひと打ち毎に、快く叩き潰されるのを感じた。
頼宣はやがて手を放した。よほど力を籠めて打ったとみえて、暫く荒い息をしていたが、
「……二十年も予に仕えながら」
と顫を帯びた声で云った。
「その方にはまだ予の気持が分らぬのか。……先日火事のおり、命を冒して宝物を取出し、また角櫓を防ぎ止めたことは手柄であった、遖れよくしたと褒めてやりたかった、しかし予は一言も褒めなかった、他の者には恩賞をやったが、その方にはなにも沙汰しなかった。沙汰せずに置いても予の気持は分るであろうと思ったからだ」
「恐れながら、恐れながらお上」
半九郎は噎びながら頼宣の言葉を遮った。
「わたくしの不調法、申訳の致しようもございませぬ、なれど此度のことは、お沙汰のなきことを不平に思った次第ではございませぬ、左様な心は些かも、些かも……」
「泣き声では分らぬ、はっきりと申せ、それではなぜ自儘に番頭をやめたのだ」
「周囲の批判やむを得なかったのでございます、わたくしの不調法から十七人の組下まで御恩賞に漏れたと申されまして、番の頭としての責任を執ったのでございます」
「周囲の批判がそんなに大事か」
頼宣はむしろその一本気を笑うように、
「世間の評判などは取止めのないものだ、そんなものに一々責任を執っていて、まことの奉公が成ると思うか。……火事場の働き遖れではあるが、沙汰をしなかったには訳がある。城は一国の鎮台として重要なものだ、宝物もまた家に取って大切だ、しかし人間の命には代えられぬぞ、火事はそのときの旱き、風の強さで、防ぎきれぬことがあるものだ、城も焼けよう、宝物も灰になろう、それは人力で如何とも防ぐことの出来ぬ場合がある」
「その方の働きは遖れであったが」
と頼宣は静かに続けた。
「もしその働きを賞美したら、これからさき多くの家臣たちが、その防ぎきれぬ火に向かって、もっと危険を冒すことになるだろう。城は焼けても再び建てることは出来る、だが死んだ人間を呼返す法はないぞ。……心のなかでは褒めながら、そうしなかった理由はそこだ、予にとっては城よりも宝物よりも、家臣の方が大切なのだ。角櫓一つ助かるよりもその方の無事であることの方が予にはうれしいのだ、半九郎」
半九郎の背が見えるほど波を打ち、砂を噛むように歔欷の音がもれた。
「二十年も側近く仕えながら、その方にはこれだけの気持すら察しがつかぬのか、周りの批判は聞き咎めても、予の心を察する気にはならぬのか」
「……申訳ござりませぬ」
半九郎は身を絞るように呻いた。
「それほどの思召とも存ぜず、愚な執着に眼が昏んで居りました、このうえは唯……御免」
云いながら、ツと脇差へ手をかけた、しかし咄嗟に頼宣がその利腕をがっしと掴んだ。
「馬鹿者が! なにをする」
「お慈悲でございます、わたくしに腹を」
「ならん!」
頼宣は有名な強力である、半九郎の懸命の腕を押えつけ、脇差を鞘ごと脱ってすっくと立った。
「死なして宜いなら予が手打ちにして居る、その方がいますべきことは切腹ではない、小次郎との仲直りだ。……小次郎まいれ」
振返って叫ぶと、小松原の中から畔田小次郎が走り出て来た。そして半九郎の傍へ並んで平伏した。
「その方共は自儘に果合いをしようとした。軽からぬ罪だ、両人とも五十日の閉門を申付ける、ただし小次郎も半九郎の家で、一緒に謹慎して居れ、離れることならんぞ」
頼宣はそう云って去って行った。右手の拳を揉みながら、
「恐ろしく固い頭だ」
と呟くのが聞えた。
二人は平伏したまま泣いていた。
川霧はようやく消えて、雲を割った太陽が眩しいほどの光を、鼠ヶ島の上へさんさんと射かけて来た。……小松原の中に控えていた近習番たちを連れて、頼宣が遠く去ってしまってからも、彼等はそのまま泣いていた。
「小次郎、……己たちは仕合せ者だな」
半九郎が泣きながら云った。
「そうだ、これほどの御主君に仕えることの出来るのは、武士と生れての此上もない果報だ」
「己は自分の心の狭さが熟く分った、勘弁して呉れ小次郎、瑞枝を娶ったら、己は琴を弾かせて心の修業をするぞ、琴を聴いて、本当に心が曠くなるものならば、己は、本当に瑞枝の琴を聴くぞ」
「そう思えばそれで宜いんだ、琴なんか問題じゃない、我々はいまもっとすばらしい修業をしたんだ」
「分ってる、それは分ってる、でも己は琴を聴くよ、琴に限らない、どんな方法ででもこの心をもっと曠くしたいんだ、まことの御奉公の出来る人間になりたいんだ、己は、琴を聴くぞ小次郎」
「そうむやみに、琴々って云うなよ」
小次郎は泣きながらぷっと失笑した。
「馬鹿だな、可笑しくなるじゃないか」
それと一緒に半九郎も失笑した。
二人は泣きながら、両方の眼から、ぽろぽろと涙をこぼしながら、声を放って笑いだした。