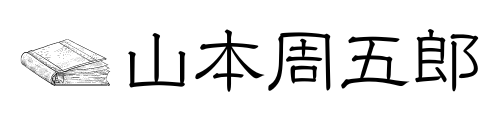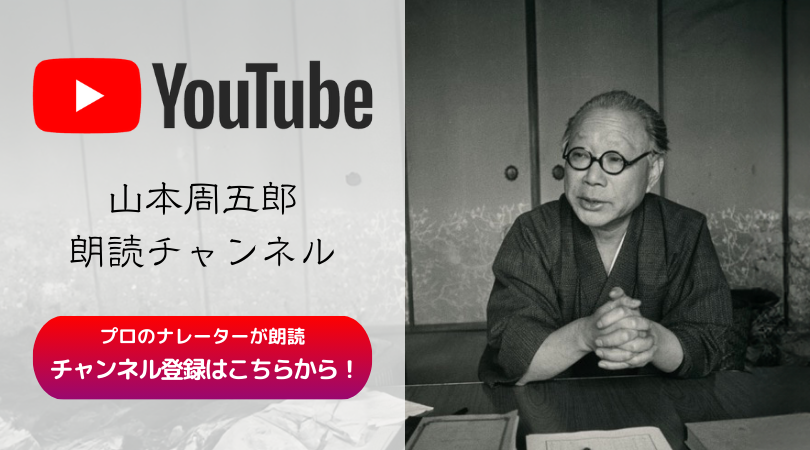『狐』

あらすじ
岡崎城の天守閣に「妖怪が出る」という噂が立つ。最初は誰も信じなかったが、番士たちが次々と異様な声や影、階段を忍び歩く足音を体験し、恐れを抱くようになる。勇猛な斧塚新五郎が「妖怪退治」に挑むが、恐怖に駆られて逃げ帰り、噂はさらに広がった。
国老次席・拝郷弥左衛門は、婿の乙次郎に調査を命じる。乙次郎は天守で夜を過ごし、番士たちの証言を確かめながら、冷静に怪異の正体を探る。そして、ある夜、階段を忍び歩く音を聞いた乙次郎は、抜き打ちで斬りつける。すると、何かが窓を突き破り、屋根の上で倒れていた。それは巨大な狐だった。
乙次郎は天守閣の修理を進言し、やがて矢狭間の隙間から白鷺が出入りしていたことや、木組みの緩みが異音を生んでいたことを突き止める。つまり、「妖怪」の正体は自然現象と動物の仕業だったのだ。しかし、人々が納得するには「形として示された事実」が必要だった。彼はあえて狐を仕留めることで噂を鎮めたのである。
その後、乙次郎の妻・美弥が、彼の元に猟師が新たな雌狐を売りに来たことを伝える。二人は顔を見合わせ、思わず笑うのだった。
本作は、噂や迷信が人の心理に与える影響を巧みに描いた時代小説であり、冷静な判断と知恵が恐怖に打ち勝つことを示した作品である。
書籍
朗読
本文
いちばんはじめに、誰が云いだしたかわからなかった、また、はじめのうちは誰もほんとうだと思う者はなかった、「まさか、いまどきそんなばかなことがある筈はない」そう云って笑う者が多かった、「そんならためしてみるか」「いいとも」そんなことがいくたびとなくあった、そうして、だんだんと笑う者がなくなった。けれども梅雨期にはいるまではそれほどひろまってはいなかった、ごく近しいなかまのあいだで、ひそひそ囁きあいはするが、内容が内容なので迂濶な者に聞かれたくないという気持がみんなにあった。それが五月(新暦六月)にはいって、じめじめした雨の日がつづくようになったある夜、さらに思いがけない出来事がおこって、噂は本丸やぐら番ぜんたいにひろまる結果となった。……その夜いつつ(八時)頃になって、非番のはずの斧塚新五郎がふいと詰所へあらわれた。しかも、かなり酒に酔っているらしい、かれは詰所へはいって来ると、詰めていた十人の番士たちをぐるっと見まわして、
「おい、貴公たちみんな知っているのか」といきなり云った。そこにい合わせた者の半数にはなんのことかわからなかった、すぐわかった者も黙っていた、「お天守に妖怪がでるという話を聞いたんだ、貴公たちも知っていたんだろう」
知っている者も知らない者もただ妙な顔をした。新五郎はちから自慢で武ばった男だった、じぶんで寛永武士を気どっていて、口をあくと当世(享保年代)ぶりを軽侮するのが癖であった。父の代までは旗本の先手組だったが、かれが相続してから徒士になり、いまでは平の櫓番である。
「返辞のできないところをみると、みんな知っているんだな、だらしのないれんじゅうだ」新五郎はかたなをとって右手にさげながらあがって来た、そして、みんなのそばへ暴々しく坐り、えんりょもなくつづけさまに酒気を吐いた、「百姓か町人ならまだしも、岡崎武士ともあるものが妖怪とはなんだ、宮内、いつごろからそんなばかな評判がたったんだ」
「さあ、拙者は知らないが……」
「茂木は知ってるだろう」
「拙者もよくは知りません、そんなことをちょっと聞いたように思いますが」
「ふん、そろいもそろって歯痒いやつらだ」新五郎は軽侮に耐えぬという眼つきで、みんなの顔を見まわしながら鼻を鳴らせた。それから、かたなを抱いて仰向に寝ころび、「もし仮りにそんなことがあったとしても、組うちの事は組うちで始末をすべきじゃないか、おれはさっき二の丸番の岸田竜弥に聞いてやって来たんだ、こんなことがよその組へ知れるなんて本丸番ぜんたいの恥辱だぞ」
「…………」みんな黙っていた。
「今夜から当分おれが天守へ泊ってやる、よつはんが鳴ったらおこせ、わかったか茂木、よつはんだぞ」
「承知しました」
かれは鼾をかいて眠った、酔っていたせいもあるだろうが、そのようすはいかにも剛胆だった。時刻がきて呼びおこされると、彼は熱い茶をなん杯ものんで天守へでかけていった。その夜もけぶるような雨だった、本丸やぐら番の詰所は月見櫓にある、天守閣はそこから二百歩ばかり西南になっていて、たいてい暗い晩でも、詰所の窓からは三重のやぐらが黒く夜空へそそり立っているのがみえる。城主が在国のときは番士はそこへ詰めているが、留守になるとみな月見櫓へひきあげ、夜なかに一回みまわりをするだけが役目のきまりだった。もっとも、かならずしもそれは励行されていたわけでなく、みまわりにでかけても天守の上へはあがらず、石垣のへんで時間をつぶして戻るというのが、番士たちの常識になっていた。
ここのつ(午前零時)をすこし過ぎたころ、なんの前触れもなくもうひとりの人物が詰所へやって来た、国老次席の拝郷弥左衛門であった。ちょうど弁当をつかっていた番士たちはおどろいて箸を投げだしながら出迎えた、「いずれもご苦労じゃ」弥左衛門は濡れた笠と合羽をとって戸口をはいった。この深更にこんな場所へなんのために国老次席がやって来たのか、誰にもちょっと見当がつかなかった、それで挨拶にも困っていると、
「わあっ」というような奇妙な叫びごえがきこえ、天守のほうから人の走って来るはげしい跫音がした、あんまりその声が異様だったので、番士たちはもちろん弥左衛門もびっくりしてふりかえった。雨水をはねとばしながら闇のなかをつぶてのように走って来たのは斧塚新五郎だった、「だ、だれだ」かれは戸口へとびこみながら、紙のように白くひきつった顔でわめきたてた、「今いたずらをしたのは、どいつだ、ここへ出ろ、いたずらをしたやつはこれへ出ろ」
かれは右手に大剣を抜いて持っていた、その白刃をつきつけながら狂気のようにわめいた。はだしで、頭からずっくり濡れていた。
朝食のまえにちょっと雲がきれ、あざやかに青い空がみえたと思ったけれども、ほんの僅かなあいだにすっかり曇ってしまい、いつかまた霧粒の舞うような、雨になってしまった。
「昨夜は夜釣りにいったそうだな」
「……はあ、いってまいりました」
「なにを釣りにいった」
弥左衛門は食後の茶をすすりながら婿の顔を見た。乙次郎はいつものとりとめのない表情で雨にけぶる庭の緑をみていた。
「なにを釣ろうというほどの、あてもありませんでした、なにか釣れるだろうと思って、ぼんやりでかけたのですが」
「なにか釣れたのか」
「さっぱりだめでした、魚釣りなどもなかなかむずかしいものとみえます」
弥左衛門はつねから、娘の婿は平凡な男でなければならぬと信じていた。とびぬけた才能をもっている者や非凡な人間はとかく圭角の多いものである。拝郷は代々老職の家がらで岡崎藩政の中軸を押えていた。そういう位置に圭角のある者がすわると政治の運用がまるくいかない、非凡な才能よりも、むしろ平凡でよいから抱擁力の大きい、人の「和」をはかることのできる人間でないといけない、弥左衛門はそう考えていまの婿をもらった。乙次郎は老職栂野騎兵衛の二男であった。弥左衛門は栂野とはちょうどよい碁敵で、しばしば往来するうちに乙次郎をみこんだ。どこをみこんだのか自分でもわからないが、あるときかれを見ているうちに、ふいと決心がついたのである。娘の美弥が十七、乙次郎が二十三歳でとしまわりもよかった。去年の二月に祝言をしてもう一年以上になるが、夫婦の仲もうまくいっているようすだった。
しかし弥左衛門の気持はこのごろすこし不安になってきた。一年あまりにもなるのに、婿のようすが茫漠として、まったくつかみどころがないのである。栂野にいた時分からひきつづき書院番の頭をつとめているが、城中でも屋敷でもまったくいるのかいないのかわからない、用事があったり思いついたりしていってみると、城中にいる時刻にはちゃんとその役部屋にいるし、屋敷にいる時刻にはかならずその居間にいた。これはみそこなったかもしれぬぞ。老年にはありがちな堪性のなさから、弥左衛門はそろそろ疑惧にかられだしていた。
「このごろ本丸で妙な噂があるようだが、聞いたことはないか」弥左衛門がさぐるようにこう云った。
「はあ、四五日まえにちょっと耳にしました」
「それなら夜釣りにゆくひまで、なにかすべきことがあった筈だと思うが」
「しかしそれほど重大なことでないと考えたものですから」乙次郎はやはり庭の緑をみたままそう云った。
「重大でないことがあるか、噂にもせよお天守に妖異があるとあってはお留守をあずかるわれらの責任だぞ」弥左衛門は婿の顔をにらみつけた。けれどもいま怒っている場合ではないと気づき、昨夜おのれがたしかめた仔細のあらましを話して聞かせた、「……新五郎はお天守の三重へ登って、まっ暗がりのなかに坐っていたそうだ、すると頭の上の方でとつぜん、異様な叫びごえがおこり、なにか白いものが宙を飛んだという」
「しとめたのですか」
「抜き打ちをかけたがおそかった。それで元のところへ坐ってゆだんなく気を配っていると、うしろの階段をそっと忍び足でおりてゆく者がある、一段ずつ、みしりみしりと、二重へおりてゆく足音が聞えたそうだ、そこで、これはやぐら番の者のいたずらだと思い、嚇となってとびおりて来たということだった」
「まだ噂はそうひろがっていないようだ」と弥左衛門はすぐにつづけた、「だが、いまのうちに始末をつけなければ岡崎城の名聞にかかわることになるかもしれぬ、書院番のほうはわしが扱って置くから、おまえ今夜にもいって妖怪の正体をつきとめてこい、今夜でいけなければ幾晩かかってもよい、正体をつきとめるまでは帰るに及ばないぞ」云うだけ云うと、老人は返辞も待たずに立っていってしまった。
乙次郎はしばらくそのまま坐っていたが、やがて自分の居間へはいった。そこでは妻の美弥が登城の服をとりだしていた。そして、はいって来た良人をみるとしずかに眼で笑いながら、「よいお役目にお当りあそばしましたこと」と云った。夜釣りにいったと聞いて父が不興そうな顔つきをしたので、心配して、そっと襖の蔭で聴いていたのである。
「なにしろもののけだからな」乙次郎は妻の笑っている眼にこたえながらそう云い、しずかに着替えをはじめた。
登城した乙次郎は、書院番のしごとを済ませてから本丸やぐらの詰所へいった、そして、みんなの話すことをいろいろと聞いた。
怪異の噂がはじまったのは桜の散りはじめるじぶんからだった、ふだん深更の見まわりに天守へあがらないのを、ある夜、ひとりの番士が登っていってみると、三重で異様なうめきごえを聞き、つづいて階段を誰かしずかにおりてゆく跫音を聞いた。そのときの「みしっ、みしっ」というしずかな、重々しい忍び足のもの音はすさまじかったという。恐怖からきた勇気で階段へとびだしていってみたが、どこにも人の姿はなかった、二重へおり、一重へおりてみると、こんどは上のほうへ登ってゆく跫音がする、やはりひどく落ちついた忍び足で、みしっ、みしっと、きわめてゆっくり登ってゆくのである、その番士は蒼くなって天守をとびだした。
ごく仲のいい男がその番士から話を聞いた、それからつぎの男、つぎの男という風に、なん人もその話を聞き、自分で天守へためしにいってみた。なにかしらみんな妖しいことに遭った、うめきごえを聞いた者もある、まっ暗な宙に白い異様なものがひらひら舞うのを見た者もある、ぞっとするような笑いごえを聞いた者もあった。みんなそれぞれ違う怪異を経験したが、誰もが一致して聞いたのは階段の跫音だった、それだけは例外なしに経験していた。
みしり……みしり……みしり。
落ちついた、ゆっくりした、そっと忍んでゆく跫音だった。こちらが登ってゆくと跫音はおりてゆく、こちらがおりてみると跫音は登ってゆくのである。たしかに妖怪のしわざだと云う者もあり、亡霊にちがいないと云う者もあった。半年ほどまえに、やはり天守番だったひとりの若侍が、つまらぬ過失を苦にやんで自殺したことがある、まだ朝々の霜のふかいじぶんで、かれは天守閣の北がわの石垣の下でみごとに切腹していた、死体の衣服に白く霜が凍っていたことを、そのとき駈けつけた同僚たちははっきり覚えている。亡霊だと主張する人々はその自殺した若侍のことを指摘して、かれの亡魂が天守番をしに来るのだと云った。
……これらの話を聞いて、乙次郎は昼すぎ屋敷へ帰った。
「ちょっと寝る支度をして呉れ」
「おかげんでもお悪うございますか」
「なに、夜詰めの用意だ」
夜具をとらせて横になった、美弥はちょっと不安になったようすで、
「ほんとうにあやかしが出るのでございますか」
「そうらしいな」
「いやでございますわ、まじめなお顔をあそばして、嘘でございましょう」
心配そうに覗く妻の美しい眸をみて、乙次郎はなにも云わずに微笑した。……弥左衛門が下城して来るのと、いれちがいに乙次郎は出ていった。しかし月見櫓の詰所へあらわれたのは八時ごろである。夕方から雨はあがっていたが、空は低く雲が垂れさがっており、梅雨期にはめずらしいひどく蒸し暑い晩だった。かれは十一時ごろまで詰所にいて、それから天守のほうへでかけていった。
「斧塚なんぞなら日頃の高慢の鼻を折っただけで済むが、国老の息子ではただしくじったでは相済まぬだろうに」「婿にはなりたくないものだ」話しながらも、みんなの耳は天守のほうへあつまっていた。いまにも乙次郎がとびだして来はしないか、なにか異変のもの音でも聞えはしないかと。
けれどなにごともなく時刻が経った、そして夜のしらじら明けに乙次郎が詰所へ戻って来た。べつに変ったようすもみえなかったが、「いかがでございました」と訊くと、彼はなぜかふと眼をそらした。
「いかにも、話のようなことがありました」
「ではやはりあの跫音をお聞きでしたか」
「聞きました」
みんな眼を見合せた。乙次郎は茶を一杯すすると、また晩に来るからと云いのこして下城した。
屋敷へ帰るとすぐにかれは寝た、案じていた妻はなにか訊きたそうだったけれども、かれのようすがそれを許さなかった。つねから口かずの寡ないほうであるが、その日はことに殻を閉じた貝のような感じだった。
その晩も、あくる晩も、かれは天守で夜詰めをしては昼のうち屋敷へ帰って寝た。弥左衛門は苛々して顔を見るたびに、「どうした、まだ埓があかぬか」とせきたてた。乙次郎はなかなか思うようにはまいりませんと云うだけで多くを語らなかった。そして四日めになって、雨のどしゃ降りに降るなかを、かれはいつもより早く、まだ日暮れまえに下僕もつれずひとりで出ていった。
乙次郎が月見櫓へあらわれたのはやはり八時ごろであった。
「今夜はすこし早くから詰めてみましょう」そう云って彼は天守へ登ったが、すこしするとふたたび詰所へあらわれた、「提燈をかして下さい」乙次郎の眼はいつもと違ってするどい光を帯びていた、かれは自分の燧袋をさぐりながらきっぱりとした調子で云った、「もしなにかあったら提燈を振ります、そのときはすぐ手をかしに来てください」そして天守へ戻っていった。
雨はざんざんと降っていた、どこか樋の損じているところがあるとみえて、櫓の横のほうで溢れ落ちる雨水の音がひときわ高くきこえている。番士たちは今夜にかぎって乙次郎のようすがひどく緊張していたのと、あまりにはげしい雨とに圧倒され、みんなかたく膝を寄せてひっそりと窓のほうをみまもっていた。……まえにも記したように、櫓の南窓からはたいてい暗い夜でも天守がみえた、しかしどしゃ降りではだめだった、それと思えるかたちもみえなかった。
「そろそろここのつではないかな」
誰かがそうつぶやいたとき、隠居曲輪の時の鐘がやっと十時をうちだした、
「なんだ、まだそんな時刻だったのか」
みんながっかりしたような顔をした。茶でも淹れかえようかと云いながら、若い番士のひとりが立ちあがった。立ちあがった彼はなんの気なしに窓のそとを見た、すると闇のかなた、かなり高いところに赤い火のたまがゆれていた。
「なんだ、どうした」若い番士の驚きのこえを聞いて、みんなぎょっとしながらふりかえった、そして、かれが窓のそとを指さしているのを見て、おっとり刀でそっちへ駈けつけた、「火のたまが、……あんなところに火のたまが」うす赤く丸い火が、ゆらゆらと闇の高い宙にゆれていた。ひとりがすぐ気づいて「拝郷どのだ、さっきの提燈だ」みんな眼を見交した。「なにかあったのだ」そして提燈が見えたらすぐ来て呉れと云った言葉がかれらの頭に甦った。
「……ゆこう」けしかけられたような調子で、誰かがそう叫んだ、その調子がみんなをうごかした、かれらは合羽を頭からかぶり、はだしのまま豪雨のなかへとびだしていった。
乙次郎は三重の階段口にいた。階段へさしだしている提燈の光が、顎から逆に照らしているので、乙次郎の顔はひどく異常なものにみえた、「ご足労をかけました」かれは右手に、抜いたかたなを持っていた。
「なにかあったのですか」
「……斬りました」えっというふうにみんなが息をつめた。乙次郎はかたなにぬぐいをかけて鞘へおさめながら、すっかり落ち着きをとりもどしたこえで云った、「そこに坐っていると、またいつものように階段を登って来る跫音がきこえました、知らぬ顔をして黙っていると、なにものかうしろへ忍び寄るようすでした、それで抜き打ちに一刀あびせたのですが、そこの窓からそとへ」云われてみんな慄然としながらふりかえった、北がわの窓格子が壊れていた、「……ぱっとそとへ飛んだものがあるのです」
「やはり、やはり、妖怪でしょうか」
「しらべてみてください」乙次郎は番士のひとりに提燈をわたした、「じゅうぶん手ごたえはあったのです、屋根の上を見てください」
提燈をさきに、番士たちは窓のほうへ近寄った、壊れている格子のあいだから、ひとりが燈をさしだすと、思いきって身をのりだした番士のひとりが、あっと云って叫んだ、「いる、毛物が倒れている、それそこのところに……」みんな怖いもの見たさに争ってさし覗いた。その窓のすぐ右がわの、屋根瓦の上に、尾のさきまでいれると五尺にあまるほどの野獣が倒れていた。はためく提燈の光で、斬り放された頸の根のすさまじい傷がみえていた。
「狐だ、おそろしく大きなやつだぞ」
弥左衛門は婿のてがらを褒めようともせず、むしろ不機嫌な顔つきをしていた。
「窓格子はひどく壊れたのか」
「すっかり造り直さぬといけないようです、ついでにお天守ぜんたい修理をすべきでございましょう、木組みがゆるんでいますし、南がわの矢狭間はひどくいたんでいて、そこから白鷺などがではいりしているようですから」
「鷺がではいりしておる……天守番はなにも云わぬが、どうしたのだ」
乙次郎はそれには答えなかった。
「修理はぜひ必要です、よろしかったらわたくしが宰領をいたします」
「ともかく、作事方へ話してみる」
弥左衛門もそのつもりになったらしい、それからすぐに天守閣へ大工がはいるようになった。かたく口止めをしておいたので、広くは騒がれなかったけれども、やぐら番の人々を中心として乙次郎を讃賞するこえが高くなった、それはかなり弥左衛門をよろこばせた。――やはりみこんだだけのことはあった。これなら拝郷の家をゆずれる、茫漠としてつかまえどころのなかった婿のなかに、はじめて骨のありどころをさぐり当てたという感じだった。そして、乙次郎を見るときの弥左衛門の眼は、ようやく温かい色をもちはじめた。
きれいに雨があがって、緑に染まったような爽やかな風のわたる日だった。非番で家にいた乙次郎が庭の泉池の鯉に餌をやっていると、裏庭のほうから妻の美弥がなにかくすくす笑いながら近寄って来た、「面白いものをごらんにいれますから、納屋までおいであそばせ」「……なんだ」「ごらんになればおわかりになりますわ」美弥はやはり笑っていた。
乙次郎は残っている餌をすっかり泉池の上へ投げやって、妻といっしょに裏のほうへいった。裏庭には十五六本の柿の木がある、その柿畑のわきに納屋があった。
「この中をごらんあそばせ」と云われて乙次郎は中を覗いた、すると茶色の毛をした一頭のかなり大きな狐が、しっかりとそこに繋がれていた、「……南村の六兵衛と申す猟師が持ってまいりました、こんどのは雌狐だそうで、先日のとちょうど番になるから買って呉れと申しまして」
「……誰かに見られたか」
「いいえ」美弥は微笑しながらかぶりを振った。
乙次郎は納屋の戸をしめ、妻といっしょに庭のほうへ戻りながらいった。
「いろいろ考えたが、そのほかにいい智恵がなかった、この世に変化妖怪のあるわけはない、けれども無いという証拠もない、番士たちが聞いた異様な声というのは損じている矢狭間を出はいりする鷺だった、宙に舞う白いものというのもそれだ、また階段に聞えた跫音というのは、木組のゆるみが緊まる音だった」
「どなたもお気づきなさらなかったのでしょうか」
「はじめに妖怪だと思いこんでいるからなにもかも怪しくなる、たとえ、いま話したことを聞いても信じられないだろう、……かたちにあらわれたもの、事実で示されたものを見るまでは、こういう噂は消せないものだ」
「狐を買いにいらしったのは、夜釣りの晩でございましたのね」
信頼と愛情のこもった眼で、美弥はつくづくと良人の横顔を見上げた。けれども乙次郎はそれには答えず、
「あの猟師はなにしにまた狐などを持って来たのだろう」
「それはあの……」猟師の話によると、このまえは五両という法外な値だったという、だから番になるようにと追っかけ雌を売りに来たのである。美弥には猟師の気持はわかった、しかし金のことになるので、良人には云えなかった、「御安心あそばせ、猟師には他言せぬように申しておきましたから」
「しかし、……あの狐をどうしよう」
夫婦はふと顔を見合せた、そして、いっしょに笑いだした。